本記事は、連載「OCXを支える技術」の一記事です。記事一覧は、本記事のタグ #OCXを支える技術 からご覧になれます。
はじめに
こんにちは。BBSakura NetworksのOCXコンテンツ制作チームです。
わたしたちBBSakura Networks(以下、BBSakura)は、NaaS(Network as a Service)(注*1)として、OCXというサービスを日々開発しています。
ただ、NaaSはまだまだ社会にとって新しい概念です。その社会的意義やメリットを、わかりやすく伝えていくにはどうしたらいいか……? エンジニアが開発したすばらしい技術を、もっと広めていくには……? そうした問いに日々考えをめぐらせています。
そこで今回は、小冊子『できるNaaS』の制作過程を通して、OCXコンテンツ制作チーム(以下、「制作チーム」と呼称)の〈技術〉について、お話していきます!
『できるNaaS』とは
『できるNaaS』とは、BBSakuraとともにOCXを共同開発するBBIX株式会社が、株式会社インプレスとともに制作した、完全オリジナル小冊子です。

NaaSについて多くの方に知っていただくために、一般向け技術解説書で30年以上の実績のある「できるシリーズ」と手を組み、特別版として小冊子を制作しました(注*2)。
全24ページで、NaaSに関する基礎知識や社会的な意義、ユースケースについて解説しています。
今後、PDF版の無償配布や、展示会などでの冊子版の配布を予定しています。
『できるNaaS』制作のきっかけ

OCXは、NaaSと呼ばれる形態のサービスのひとつです。
ネットワークをクラウドサービス化するというNaaSの基本概念は、IT技術者の方々は比較的想像しやすいかもしれませんが、一般的な認知度はまだまだ。技術に明るくない人でも、NaaSがどんなものか理解できるコンテンツを作れないか……。そんな問題意識から、今回の制作に至りました。
わたしたちが特に気をつけたのは、「正確な情報を、簡潔に表現すること」。ともすれば説明が複雑になりがちな最新のネットワーク技術情報やIT業界の動向を、なるべくわかりやすく伝えることに苦心しました。インプレス側の制作チームのお力添えもいただきつつ、よりよいものに仕上げていきました。
コンテンツの制作過程と役割
今回の制作プロセスは以下のとおりです。
事前準備・取材
関係者同士で、制作全般にかかわるルールや前提、スケジュールを共有します。また取材や打ち合わせを通して、制作の前提となる知識も共有します。
ラフ
今回のコンテンツに盛り込むべきトピックや、紙面上の配置を決めます。
初校〜再校〜最終校
デザインされた紙面に、実際の文章や図版を載せて、原稿チェックを行います。再校のあとは、三校・四校……と続くこともあります。スタッフ内で内容を合意できたら、晴れて「校了」です。
より一般的な雑誌・デジタルコンテンツの制作フローについては、以下のサイトも参考にしてみてください。
www.edit-u.com
jinji.shogakukan.co.jp

また一般的に、コンテンツ制作には、以下のような人々が関わっています(注*3)。
ディレクター/編集者
コンテンツ全体の方向性を考え、伝えたい内容を適切に表現する方法を考えます。媒体のブランドや掲載方法も勘案しながら調整も行う、制作の中心となる役割です。
ライター
文章の執筆を行います。話し言葉(口語)と書き言葉(文語)は異なるため、読みやすい文章にすべく、表現を工夫します。またインタビューや座談会の場合は、録音・録画データからテキストを文字起こしし、構成も行います。
イラストレーター
企画に沿ったイラストの制作を行います。文章では伝えづらいことを視覚で表現する大切な役割です。
DTPオペレーター
ディレクター/編集者の指示に沿って、InDesignなどのソフトを使って紙面を制作します。文章やイラストを流し込み、見た目の細かい修正を行うほか、印刷物の場合は、色味の調整を行うことも。「制作」と呼ばれることもあります。
校正・校閲
内容のファクトチェックや、誤字脱字の確認といった一次確認(素読み)から、言葉の使い方や意味に関する指摘まで行います。
今回はこうした役割を「できるシリーズ」編集部に委託しましたが、BBSakuraも制作に大きく関与しています。
偶然ではありますが、BBSakuraにはイラストが描ける人や、装丁やDTP、編集・ライティングの経験者がそろっていました。それぞれのスキルを活かし、チーム一丸となって制作に取り組みました。(本記事に掲載しているイラストも、実はスタッフの描き下ろしなんです!)
ラフ(素案)の制作
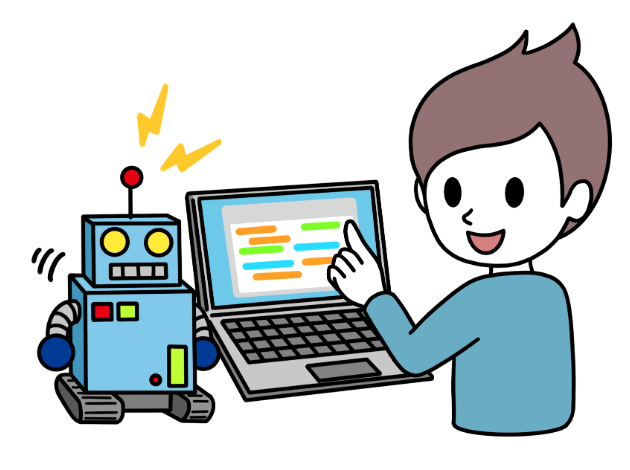
先述したように、『できるNaaS』はNaaSという言葉をはじめて聞く人も、楽しく読める内容にする必要がありました。
ですので、最初は「as a Service」という概念の説明からはじめ、セキュリティやAIといった話題にふれながらNaaSの概論に入っていくことにしました。そしてNaaSのユースケースを例示しつつ、大企業の場合・中小企業の場合・地方自治体の場合……と、各論を伝える構成にしました。最後には、わたしたちBBSakuraが共同開発するOCXを例に、その使い方を紹介しています。
イラストやビジュアルも大切な要素です。最終的な仕上がりを想像しながら、見出しやイラストの位置、文章の内容を決めていきました。また社内のエンジニアにも多くの意見をもらいました。
初校から最終稿までの制作

ラフを踏まえて、実際に「できるシリーズ」編集部から届いた原稿をチェックしていきます。クオリティをさらに高め、「正確な情報を、簡潔に表現する」ために、以下のことに気をつけました。
具体的なデータを添える
クラウドやIT業界に関する各種統計は、各省庁や企業が詳しいデータを公表しています。特に今回は総務省や経済産業省の調査データを盛り込みました。具体的な数字や事例があると、紙面の説得力もぐっと増します。もちろん、データや文書の引用をする場合は、出典を明記し、著作権法を遵守しているか、必ず確認します。
より簡潔な言い換えを模索する
テクニカルライティングと呼ばれる分野があります。業務マニュアルや技術仕様書、オンラインヘルプ作成などで、ユーザーに正確に情報を伝える手法として注目されています。わたしたちも今回の制作に当たり、テクニカルライティングを参考にし、できるだけ簡潔な表現をめざしました。
サイボウズ・仲田さんが公開している以下の資料は、たいへん参考になります。エンジニアの方も、そうでない方も、ぜひ一度目を通してみてください。
speakerdeck.com
gihyo.jp
おわりに
制作チーム一同、限られた時間で全力を尽くし、よいコンテンツが作れたのではないかと思っています。『できるNaaS』をお見かけの際は、ぜひこうした制作過程についても思い出していただけたら幸いです。
ありがとうございました!